| 鴨居第八地区 | 鴨居原農専区域の風景 |
| 鴨居第八地区は鴨居原農専区域から、バス停地蔵前の道路を越えて竹山団地下の竹山の一部も含む地域です。学校区は3つの小学校と2つの中学校があり、諸行事の豊な地域でもあります。 そして、地域の殆どが鴨居町の町名を継承している地区です。独自で鴨居第八地区自治会館を持っています。 鴨居原農専区域は畑と山肌でしたが、農地造成の折に遺跡が発掘されました。付近の切通しには貝塚も散見され、昔の鎌倉街道とも言われておりました。 |
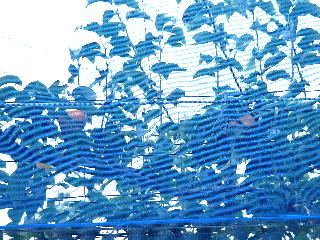 実った”はま梨” |
| 地域の情報(3) |
| 鴨居第八地区 | 鴨居原農専区域の風景 |
| 鴨居第八地区は鴨居原農専区域から、バス停地蔵前の道路を越えて竹山団地下の竹山の一部も含む地域です。学校区は3つの小学校と2つの中学校があり、諸行事の豊な地域でもあります。 そして、地域の殆どが鴨居町の町名を継承している地区です。独自で鴨居第八地区自治会館を持っています。 鴨居原農専区域は畑と山肌でしたが、農地造成の折に遺跡が発掘されました。付近の切通しには貝塚も散見され、昔の鎌倉街道とも言われておりました。 |
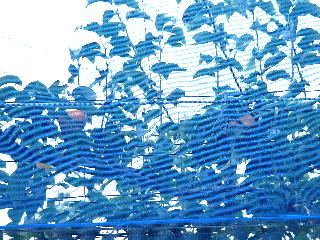 実った”はま梨” |
| 鴨居の昔からの地名 |
| 樋口(ひぐち)⇒殿谷戸と霧ヶ谷戸から流れ出る水は、すべて樋口から鶴見川に注がれた。大水が出ると逆流するので、口を止めた。樋口は出口の意味。 馬洗場⇒鴨居近隣では「うまれど」と言う。江戸時代から昭和の初めまで現鴨居自動車学校入口の辻が馬洗場であった。神奈川宿、川崎宿、保土ヶ谷宿などに出かけた人馬は疲れきって、ここで馬を休め体を洗ったり、農耕で疲れた馬を洗ったりした。 船河原⇒鴨居橋左側付近に舟つき場があり、昭和初期まで古い壊れた舟が三、四艘あった。 おんだし⇒鴨居川の出口の右側を言う。川の土と泥水を鶴見川に押出したことから言う。 高倉⇒鴨居川の出口の左側を言う。昔は島であったようで、ここは荷物の集積場で大型船が入っていた。 松場⇒鴨居4丁目64番付近〜鴨居町920番地辺りまでを言い、鎌倉街道沿いにある。 的場⇒松場の東側を辻畑とも言った。鴨居に砦があってその中にあった弓道場のことから地名となる。 作馬(つくれば)⇒鴨居に砦があったことの名残り、馬を育て訓練した所と言われている。 馬捨場⇒阿弥陀谷大坂の途中、(右側斜面竹山1丁目付近)に馬捨場があった。明治八年の調査では一畝十九歩の土地が付いていた。病気や年老いて亡くなった馬をここに埋葬したもので供養碑が建っていた。開発で無くなったのが、平成五年西谷戸講中が五飯(ごはん)塚脇に新しい供養碑を建てた。 堂坂⇒現白山町に出る近道。藤池氏のおくの方の山に山伏が住んでいたという話があり、お堂があった。団地造成中、お堂のあった所に墓が一基あり藤池弥市氏が立会いを頼まれた。骨は出てこず墓石は林光寺に納められた。お堂は山伏系のものと推察される。明治の初めころまであった。 宮久保⇒杉山神社の前の山、不動山をさしていたらしい。 一の沢⇒旧鴨居会館の前を言った。 (鴨居史より) |